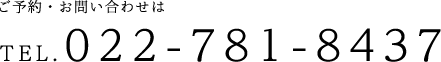▼目次
1. 根管治療の専門医とは?一般歯科医との違い
2. 日本と海外での根管治療専門医の制度の違いと背景
3. なぜ一般歯科医では対応が難しい根管治療の症例があるのか
4.仙台市の歯医者 奥州仙臺Premiumデンタルクリニックの根管治療について
歯の奥深くにある神経に問題があるときに行われる「根管治療(こんかんちりょう)」は、非常に繊細で専門性の高い治療です。しかし、患者さんの中には「どの歯科医院でも同じでは?」「専門医に頼む必要があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実際、根管治療には「専門医」と呼ばれる特別な訓練を受けた歯科医師が存在し、特に難しい症例ではその技術力が治療の成否を左右することもあります。今回は、根管治療の専門医と一般の歯科医師の違い、日本と海外での制度の違いについて詳しく解説します。
1. 根管治療の専門医とは?一般歯科医との違い
根管治療の専門医とは、歯の根の中にある神経や血管が通る管(根管)を専門に治療する歯科医師のことです。一般の歯科医師も根管治療を行うことはできますが、専門医はその分野における高度な知識と技術を習得しており、難易度の高い症例にも対応可能な場合があります。
①教育と研修の違い
専門医は大学病院などで数年間の専門研修を受けたうえで、学会などが認定する試験に合格する必要があります。一方、一般の歯科医師は歯学部卒業後、幅広い分野の診療を行う中で根管治療にも対応しますが、専門的な訓練は受けていないことが多いです。
②使用する機材の違い
専門医は、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)やニッケルチタンファイル、高度な画像診断装置などを駆使して、精密な治療を行います。一般の歯科医院では、こうした設備が導入されていない場合もあります。
③対応可能な症例の違い
再治療が必要な根管や、複雑な形態をした根管など、成功率が下がりやすい症例も、専門医であれば高い精度で対応可能な場合があります。
④治療期間と通院回数の差
専門医は精度の高い治療により、少ない通院回数で治療を終えるケースもあります。
専門医と一般歯科医の違いを理解することで、自分の症例に適した医療機関を選びやすくなるでしょう。
2. 日本と海外での根管治療専門医の制度の違いと背景
根管治療の専門医制度は、国ごとに仕組みが大きく異なります。特に、日本とアメリカを比較すると、その教育制度や資格認定の厳しさに差があることが分かります。
①日本では専門医制度が限られている
日本国内では「根管治療専門医」という資格は、いわゆる認定医制度の一部として存在しますが、国の認定制度ではありません。日本歯内療法学会が認定する「専門医」資格がありますが、ある施術のみ研鑽を重ね専門に治療する歯科医師を「専門医」と呼ぶ場合もあります。
➁海外、特にアメリカでは専門医制度が確立されている
アメリカでは「Endodontist(エンドドンティスト)」と呼ばれる根管治療専門医が国家資格レベルで存在します。歯学部卒業後、さらに2〜3年の専門教育プログラム(専門医課程)を修了することが必須で、厳格な試験をパスする必要があります。
➂海外では紹介制が一般的
アメリカなどでは、一般歯科医からの紹介で専門医に行くという仕組みが一般的です。これは専門性の高い治療は専門医が担当し、それ以外は一般歯科医が担当するという役割分担が確立しているからです。
④日本はワンストップ型が多い
日本では1つのクリニックで幅広い治療を行う「ワンストップ型」が多く、患者さんが自ら専門医を探すことが一般的ではありません。そのため、複雑な根管治療でも専門医でなく、一般歯科医が対応しているケースが多く見られます。
⑤制度の違いが治療結果にも影響
専門医制度の整備状況は、治療結果にも影響する可能性があります。例えば、海外では専門医が対応することで再治療率が低い傾向にある一方、日本では再治療が必要になるケースが多いという報告もあります。
海外のように専門性に応じて歯科医師が役割分担する仕組みは、患者さんにとっても治療の質を高めるメリットがあります。今後、日本でもこうした制度の整備が進むことが期待されます。
3. なぜ一般歯科医では対応が難しい根管治療の症例があるのか
根管治療は、歯の奥深くにある非常に細い管を清掃・消毒し、再感染を防ぐための処置を行う繊細な治療です。症例によっては、その難易度が大きく異なるため、一般歯科医では対応が難しいケースも存在します。
①複雑な根管構造
歯の根管は人それぞれで形状が異なり、枝分かれや曲がりがある場合も珍しくありません。こうした複雑な構造は、肉眼での確認が難しく、一般的な器具では処置しきれないことがあります。
②再治療が必要な症例
一度治療した歯が再び痛みを起こすケースでは、残った感染物質の除去や再充填が必要です。こうした処置にはマイクロスコープやCTなどの機材が求められ、技術も高度になります。
③穿孔(せんこう)や器具の破折
過去の治療で歯根に穴が開いてしまったり、器具が中で折れてしまっていたりする場合、特殊な対応が必要となります。これらは専門医でないと適切な対応が難しい可能性があるケースのひとつです。
④痛みや腫れの原因が不明確
根の病変が明確に映らない場合、痛みの原因が特定できず、診断力が問われます。マイクロスコープや拡大視野下での診断が有効です。
➄治療失敗のリスク軽減
複雑な症例ほど治療の失敗率が高まるため、専門医が処置することで再治療のリスク低減の可能性があります。
このように、精密性が求められる症例では、専門的な知識と経験が不可欠です。
4. 仙台市の歯医者 奥州仙臺Premiumデンタルクリニックの根管治療について
仙台市の歯医者 奥州仙臺Premiumデンタルクリニックは、歯を残すことに特化した根管治療を提供しています。マイクロスコープを用いた精密治療で患者さんの大切な歯を守ります。
歯を残すためには今ある歯を正しく診査・診断した上で治療方針を決定する必要があります。そのためには治療前にレントゲン・CT撮影や口腔内の温痛、冷通、打診痛などの検査、患者さんご自身からのヒアリングなど診査・診断を丁寧に行います。その結果を元に患者さんの生涯のお口の健康を考えた治療法を提案いたします。
また、根管治療を成功に導くためには歯と歯周組織に細菌感染が再び起こらない環境で治療を行う必要があります。そのために器具は滅菌済みや使い捨て(新品)を使用し、ラバーダムという特殊なゴムで唾液による細菌感染を防ぐなど「無菌的環境下」で治療を行うことも大切です。
「かかりつけの歯科医院で抜歯が必要と言われた」「歯の根の治療(根管治療)を何回も繰り返している」「治療後に歯や歯茎にずっと違和感がある」など、自分のお口に不安がある方は奥州仙臺Premiumデンタルクリニックにご相談ください。
まとめ
根管治療は非常に繊細で、症例によっては一般の歯科医師では対応が難しいこともあります。専門医は、高度な技術と設備をもとに、複雑な症例や再治療にも対応できる可能性があるのが大きな特徴です。また、日本と海外では専門医制度や治療方針にも違いがあり、それぞれの背景を理解することも適切な選択に繋がるでしょう。
仙台市で根管治療の専門的な対応をご希望の方は、奥州仙臺premiumデンタルクリニック 卸町までお問い合わせください。
監修
奥州仙臺Premiumデンタルクリニック
TOKU根管治療専門室 鈴木篤太郎